子どもが片付けをしない、何度言っても同じところに物が散らかる――そんな悩みを抱える親御さんは少なくありません。実は、子どもの片付けには「習慣化」と「サポート」が欠かせません。
本記事では、子どもが自然と片付けに取り組めるようになるための親の声かけや、具体的な支援方法、そして楽しく片付けに取り組める工夫について、原因・サポート方法・工夫の3つの視点から詳しくご紹介します。
片付けを難しくしている原因
1. 物が多すぎて選べない
子どもの持ち物が増えすぎると、片付けが困難になります。おもちゃ、文房具、洋服、工作、景品やおまけ……。子どもにとって「どれを使うべきか」「何が大切なのか」が判断できなくなるのです。
結果として、「全部大事」「どこに戻していいか分からない」となり、散らかったままに。
特に年齢が低いうちは、物への執着が強く、1つひとつを大切にする気持ちも芽生える時期。大人が不要と思う物でも、子どもにとっては宝物である場合があります。
2. 片付けるスペースが整っていない
物の場所が決まっていなかったり、収納が子どもの手の届かない高さにあったりすると、片付けたくても片付けられません。
例えば、「箱はあるけど中がごちゃごちゃ」「種類ごとに分かれていない」「戻す場所が1つに決まっていない」など、子どもにとって“ルールが分かりづらい”状態が続いていると、片付けのモチベーションも下がります。
3. 片付けのやり方が分からない
子どもは大人が思っている以上に、「どこから手をつけていいか分からない」状態になっています。
例えば、全部を一気に片付けようとして挫折したり、「とりあえず机の上に乗せておく」「袋に詰める」といった対処に終始してしまったり。
これは、まだ“片付けのスキル”が身についていない証拠であり、段階的に学んでいく必要があります。
片付けへのスタンスとサポート方法
子どもは「片付けを練習中の存在」
大人のように完璧に片付けられなくても当然です。何度も試し、失敗しながら少しずつできるようになるものと捉えましょう。
「命令」ではなく「問いかけ」と「選択肢」を
「早く片付けて!」「また散らかってる!」ではなく、「どれを大切に使いたい?」「このおもちゃ、どこに帰るかな?」という問いかけを意識することで、自発的な行動を促します。
処分するものは子供が決めること
アドラー心理学では「自分で選び、自分で決めること」が、子どもが自立するための重要なプロセスとされています。親が一方的に「これはもういらないでしょ」と判断して処分すると、
- 「親が勝手に決める」
- 「どうせ何を言っても無駄」という無力感を与えてしまいます。
一方で、自分で「これは残す」「これは手放す」と選ぶ経験は、物事を判断する力(選択眼)や自己決定感を育てます。
また、「○○が決めていいよ」と言われることで、子どもは
- 「ぼく(わたし)の考えを大事にしてくれている」
- 「自分の持ち物を自分で管理できる力があると思われている」
と感じます。
これが、自己肯定感や親子の信頼関係にもつながります。
1. 物が多すぎる場合のサポート
- 親が勝手に捨てるのではなく、選ばせることを重視しましょう。
- 「これはまだ遊ぶ?」「これ、誰かに譲ってもいいかな?」など、物と向き合う時間を一緒に持つことで、“選ぶ力”を育てます。
- 数を減らすのは、「管理できる量に調整する」という目的です。選びやすい=片付けやすい、につながります。
2. 収納が整っていない場合のサポート
- 子どもの目線・手の届く範囲で収納を作る。
- ラベルを貼ったり、色や形で分類しやすくしたり、写真を使うと効果的です。
- 収納場所を一緒に決めることで、子ども自身がその場所を「自分の居場所」として認識しやすくなります。
3. 片付け方が分からない場合のサポート
- 「全部出す → 分ける → 戻す」という基本ステップを一緒に体験。
- 口頭だけでなく、実際に親が手本を見せて一緒にやってみることが大切です。
- 小学校高学年くらいまでは、片付けの練習期間と捉えて、「繰り返しやりながら覚える」スタンスで関わりましょう。
片付けが楽しくなる工夫7選
1. タイマーでゲーム感覚に
「3分チャレンジ」「好きな曲が終わるまで」など、時間を区切って競争感を加えることで、集中力もアップします。
2. 音楽で“おそうじダンス”
お気に入りの音楽をかけて一緒に踊りながら片付けをすることで、気分も明るくなり、自然と動き出せるように。
3. ラベルやイラストで場所を明確に
文字が読めない年齢の子には、写真やキャラクターシールを使うのが効果的。見ればわかる工夫が、片付けのハードルを下げます。
4. 片付けリーダーを任命
「今日はあなたがリーダー!ママを手伝ってくれる?」と役割を与えることで、責任感とやる気が育ちます。
5. お気に入りの収納グッズを選ばせる
収納ボックスやかごを子どもに選ばせることで、「使いたい」「片付けたい」という気持ちに繋がります。
6. ビフォーアフターで達成感を
片付け前後の写真を撮って、「すごいね!きれいになったね」と見比べると、達成感が得られ、継続のモチベーションに。
7. 「ありがとう」「助かったよ」の声かけ
片付けたことをしっかり認めて、感謝の気持ちを伝えることが、子ども自身の自己肯定感を高め、次も頑張ろうという意欲につながります。
まとめ:子どもが片付けを楽しめる環境づくりを
子どもが片付けられないのは、「やる気がないから」ではなく、「方法を知らないから」「物が多すぎるから」「環境が整っていないから」など、いくつかの原因があります。
大切なのは、子どもを責めることではなく、状況や発達段階に合わせて環境を整え、サポートをしていくこと。
片付けは、単に物を戻す作業ではなく、「考える力」「選ぶ力」「整える力」を育てる学びの場でもあります。今日からできる声かけや工夫を取り入れて、親子で楽しく片付けを進めていきましょう。
“片付け=楽しい”と感じられる経験を積むことが、将来につながる整理整頓の力を育てる第一歩です。
参考
| アドラー式「言葉かけ」練習帳 子どもが伸びる!自信とやる気が育つ!/原田綾子【1000円以上送料無料】 価格:1,430円(税込、送料無料) (2025/7/27時点) |
アドラー心理学に基づく『アドラー式「言葉がけ」練習帳』は、子育てや職場などで相手のやる気や自立心を引き出す具体的な言葉がけを学べる実践書です。否定的な表現をポジティブに変える練習や課題の分離を通じ、穏やかで対等な関係づくりをサポートします。日常で使えるフレーズが豊富に載った必携の一冊です。

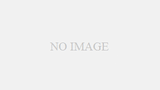
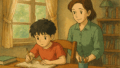
コメント